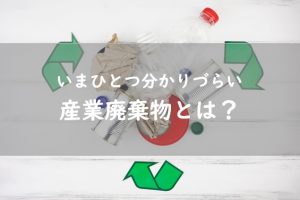専ら物とは

専ら物とは
まず、専ら物は「もっぱらぶつ」と読みます。正式名称は「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物又は産業廃棄物」と言い、リサイクルが主な目的となる廃棄物を指します。
最大の特徴は、専ら物の取り扱いには一般廃棄物及び産業廃棄物の各種許可やマニフェストの交付が不要な点にあります。
そのことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃掃法)の第七条、第七条六項、第十四条、第十四条六項にも明記されています。
ただし、廃棄物であることには変わりはなく、廃掃法の適用を受けるため、委託契約書は必要になります。
第七条(一部中略)
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第七条六項(一部中略)
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第十四条(一部中略)
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第十四条六項(一部中略)
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
専ら物の品目
廃棄物において、専ら物に該当する品目は以下の4品目になります。
- 古紙(紙くず)
- くず鉄(鉄くず)
- 空きびん(ガラスくず)
- 古繊維(繊維くず)
環境省令の「4 産業廃棄物処理業」内において「産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。」とあります。
これは令和5年2月に環境省より通知された「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)」にも改めて明記されています。
古来より、専ら物4品目を扱う小規模事業者(リサイクル業者)が存在しており、昭和45年に施行された廃掃法で一律に規制を行なうとリサイクルが円滑に実施されなくなる可能性があるため、いわば特例的に4品目は扱われているという経緯があります。
専ら物の処理方法
専ら物は「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物又は産業廃棄物」とあるように、その処理はマテリアルリサイクルでなければいけません。
マテリアルリサイクルとは、廃棄物を新たな製品の原料として再利用するリサイクル手法です。例えば、古紙ならば新聞紙やトイレットペーパーへのリサイクル、空きびんならばガラスびんや造粒砂へのリサイクルなどを指します。
つまり、古紙を焼却処分する、空きびんを埋め立て処分するなど、マテリアルリサイクルではない処理を行なうことはできません。そのような処理を行なう場合は産業廃棄物として扱わなければならず、異なる契約書、各種許可、マニフェストの交付が必要になります。
有価物との違い
専ら物は各種許可やマニフェストの交付が不要な点から、有価物と混同されがちですが、性質が大きく異なるため、全くの別物となります。
有価物は「価値があるため、他人に有償で譲渡できるもの」であるため、廃棄物の定義から外れます。つまり、有価物は専ら物とは異なり廃棄物ではないため、そもそも廃掃法の適用を受けません。それ対して、専ら物は前述のように一部特例的に扱われてはいますが、廃棄物であるため、廃掃法の適用を受けます。
まとめ
・専ら物とは古紙(紙くず)、くず鉄(鉄くず)、空きびん(ガラスくず)、古繊維(繊維くず)の4品目
・委託契約書は必要だが、各種許可とマニフェストの交付は不要
・処理はマテリアルリサイクルでなくてはならない
・専ら物は有価物ではなく廃棄物のため、廃掃法の適用を受ける